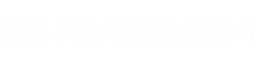NEWS
ブログ- ブログ
- 8月2日は『空き家ゼロの日』です。
2025/08/02
8月2日は『空き家ゼロの日』です。
8月2日『空き家ゼロの日』に考える、空き家という時限爆弾
毎年8月2日は『空き家ゼロの日』です。
「0802」を『空き家ゼロに』と読む語呂合わせから、空き家問題への意識を高め、その解決に向けた取り組みを促進する目的で制定されました。
ともすれば遠い問題に聞こえるかもしれませんが、これは日本の未来を左右しかねない、深刻な「時限爆弾」なのかもしれません。
今回は、『空き家ゼロの日』を機に、この問題の現状、背景、そして私たちにできることは何かを深掘りしてみたいと思います。
過去最多 900万
総務省が発表した『令和5年住宅・土地統計調査』の結果は衝撃的でした。
2023年10月1日時点での日本の総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%、空き家数は実に 900万戸に達し、いずれも過去最高を記録しました。

この数字は、日本の住宅の約7戸に1戸が空き家であることを意味します。
単に誰も住んでいない家が多いというだけではありません。
問題は、その『質』にあります。
900万戸のうち、賃貸用や売却用、あるいは別荘などを除いた「その他の住宅」、つまり活用もされず放置されている可能性が高い空き家は 385万戸にのぼり、この 5年間で 37万戸も増加しているのです。
これらの放置された空き家が、様々な問題の火種となっています。
では、なぜこれほどまでに空き家は増え続けているのでしょうか。その背景には、日本が抱える構造的な課題が複雑に絡み合っていると考えられます。
第一、人口減少と少子高齢化。
地方を中心に人口が減少し、家の住み手がいなくなる。
また、高齢の親が介護施設に入所したり、亡くなったりした後、実家が空き家となるケースが急増しています。
子どもが都市部で独立している場合、遠隔での管理は難しく、結果的に放置されてしまうのです。
第二、新築住宅の供給過多。
『新築信仰』とも言える価値観が根強い日本では、中古住宅市場が成熟しておらず、住宅の総数が世帯数を大幅に上回る状況が続いています。
第三、相続の問題。
相続登記がされないまま所有者が不明確になったり、複数の相続人間で意見がまとまらなかったりすることで、売ることも貸すこともできず、塩漬け状態になってしまうケースが後を絶ちません。
放置された空き家がもたらす多様なリスク
一軒の空き家が放置されることで、その影響は所有者個人の問題にとどまらず、地域社会全体に及ぶ負の連鎖を生み出します。
1. 防災・防犯上のリスク
老朽化した家屋は、地震や台風などの自然災害で倒壊・崩壊し、近隣の家屋や道路を塞ぐ危険性をはらんでいます。
屋根材や外壁が飛散し、周囲に被害を及ぼすこともあります。
また、人の出入りがないため放火のターゲットにされたり、不審者の侵入や犯罪の温床になったりするなど、地域の治安を悪化させる要因にもなります。
2. 衛生・景観の悪化
庭の雑草は繁茂し、害虫やネズミなどの害獣の発生源となります。不法投棄の場所にもなりやすく、景観を損なうだけでなく、悪臭や衛生上の問題を引き起こし、近隣住民の生活環境を脅かします。
美しい街並みや田園風景の中に、一軒でも荒れ果てた空き家があれば、その地域の魅力は大きく損なわれてしまいます。
出島不動産相続相談所
3. 経済的損失とコミュニティの衰退
空き家が増えれば、その地域の不動産価値は下落します。
活気が失われ、新たな住民を呼び込むことが難しくなり、商店の閉鎖や公共交通の縮小など、地域コミュニティそのものの衰退につながりかねません。
これは、地方だけの問題ではなく、都市部の郊外でも深刻化しています。
国の本気度がうかがえる法改正と対策
この深刻な事態に対し、国も手をこまねいているわけではありません。
2015年に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)』は、2023年12月に大きな改正を迎えました。
この改正のポイントは、これまでの『除却(解体)』一辺倒から、空き家を地域の資産として「活用」する方向へと大きく舵を切った点にあります。
ポイント1 『管理不全空家」の新設と固定資産税の優遇除外
最も大きな変更点は、倒壊などの危険が差し迫った『特定空家』になる前の段階である『管理不全空家』というカテゴリーが新設されたことです。
窓ガラスが割れていたり、雑草が生い茂っていたりするなど、放置すれば特定空家になる恐れがある状態と自治体が判断した場合、所有者に対して指導・勧告を行います。
この勧告を受けると、住宅用地として受けていた固定資産税の優遇措置(最大で評価額の6分の1に軽減)が解除され、税負担が最大で約6倍に跳ね上がることになります。
これは、所有者責任をより厳しく問い、『放置』という選択肢を許さないという国からの強いメッセージと言えるでしょう。
ポイント2 活用促進のための規制緩和
改正法では、『空家等活用促進区域』という制度が創設されました。
自治体がこの区域を指定すると、区域内の空き家は、接道義務(建築基準法で定められた、建物の敷地が道路に接していなければならない義務)が緩和されたり、用途変更がしやすくなったりします。
これにより、これまで建て替えやリノベーションが難しかった空き家を、店舗や宿泊施設、地域交流拠点などとして再生しやすくなります。
ポイント3 担い手支援と所有者不明空家への対応
空き家の管理や活用を担うNPO法人などを『空家等管理活用支援法人』として自治体が指定し、所有者に代わって管理や活用を進める仕組みも強化されました。
また、相続登記がされず所有者が見つからない空き家についても、市町村が家庭裁判所に財産管理人の選任を請求できるようになり、より円滑に処分や活用が進められる道が開かれました。
【負債】から【資産】へ。未来を拓く空き家活用の可能性
法整備が進む一方で、全国各地ではすでに空き家を【負債】から【資産】へと転換する、創造的な取り組みが生まれています。
栃木県栃木市では、空き家バンクに登録された物件の改修費用に対する手厚い補助制度などを設け、移住者と空き家を繋ぐことで、全国トップクラスの成約件数を誇ります。
徳島県神山町では、古民家を改修してIT企業のサテライトオフィスとして誘致し、若者の移住と新たな雇用を生み出すことに成功しました。
活用のアイデアも多岐にわたります。
カフェやレストラン、シェアオフィスやコワーキングスペースはもちろんのこと、インバウンド需要を見据えたゲストハウスや、グループホームなどの福祉施設、アーティストのアトリエ兼ギャラリーなど、地域のニーズや特性に合わせた多様な再生事例が生まれているのです。
最後に【空き家ゼロの日】から始める自分ごと化
空き家問題は、もはや他人事ではありません。
親が住む実家の将来、自身の住まいの終活、そして何よりも私たちが暮らす地域社会の持続可能性に直結する課題です。
『空き家ゼロの日』をきっかけに、まずはこの問題に関心を持つことから始めてみませんか。
そして、もし あなたが空き家の所有者であるならば、放置という選択がいかに大きなリスクを伴うかを再認識し、売却、賃貸、あるいは地域のための活用など、次の一手を専門家や自治体に相談してみてください。
空き家は、正しく向き合えば、新たな価値を生み出す『地域の資源』となり得ます。
一軒一軒の空き家が再生され、再び人の営みの灯がともる時、それは単に空き家が一つ減るということ以上の意味を持ちます。
それは、地域の安全を守り、景観を育み、新たな交流と活気を生み出す、未来への投資となります。
空き家問題の解決は、私たち一人ひとりが当事者意識を持つことから始まると思います。